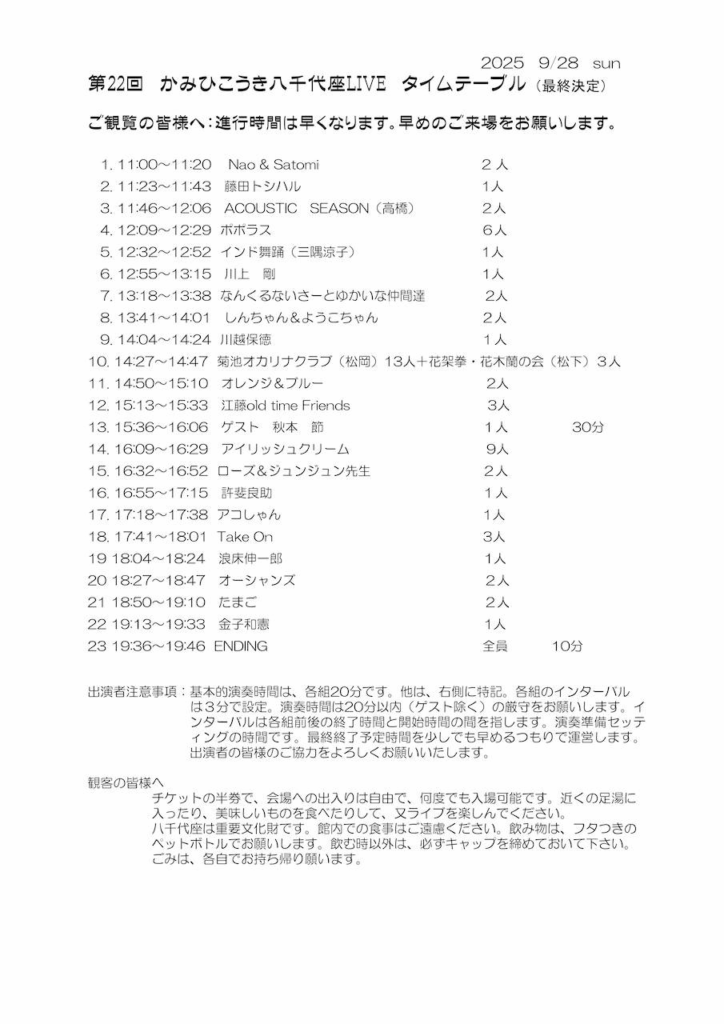残業の単価計算方法ってご存じですか?
残業は1時間単価に残業時間を掛けて計算します。
残業時間については、以前は1時間単位で計算していました。
なので、30分単位で切り上げ、切り捨てしてたりしてました。
しかし、今はPCで簡単に計算ができますので、残業時間は分単位で計算することとなっています。
一ヵ月の残業時間を足し上げて、分単位で集計します。
5時間29分、みたいな数字で全然OKです。
これに時間単価を掛けます。
例えば、残業単価が1,500円であれば、
1,500円×5時間29分=8,224.9円
となります。
時間の計算はわかりやすいですが、残業単価の計算はややこしいです。
これが、元々時給の場合は簡単です。
残業は25%割り増し(※深夜や休日は異なる)なので、
時給が1,200円であれば、1,500円となります。
問題は月給の場合です。
どうやって時給単価を計算するのでしょうか?
説明が長くなるので、続きます。。。